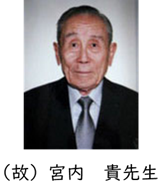 ―そして開業医、やがて市整会―
―そして開業医、やがて市整会―
昭和44年頃だったと思いますが、われわれ「ひよっこ」開業医たち(松井、吉田、宮内など)は、日々いろんなことで、なやんでおりました。
いわゆる開業医術、保険請求、節税、薬品購入などなどの問題、そして孤独感からの開放などをたよって、人の話を聞いて参考にしようと、飲みながら、食べながら、だべって2-3年が過ぎました。しかし、我々だけでは限界がありますので、もっと先に開業された経験豊富な先生方(伊藤、大村、広谷、有馬、松尾、和田先生など)にお願いして、親睦と情報交換など勉強させて戴くようお願いしました。諸先生方は快くご承諾戴きまして、数回寄合をしました。当時、開業されている同門の先生方は30名近くになっておりました。
その頃、開業医は大学病院、関連病院からは軽くあつかわれ、相手にしてもらえませんでした。大学病院に患者紹介しても、そっけないし、返事ももらえないし、軽々にあつかわれていました。開業医は孤独でした。
この現状を何とかしたい、そとに向かって「もの」が言えるような組織、すなわち「会」を作って、皆様方に入会して戴き、勉強し、情報交換し、親睦を深めて、そして大学病院や関連病院などに「もの」が云える会にしてはどうか?と、とてつもないことを考えたのが開業医会のはじまりでした。教室に同窓会という組織がありながら、更にまた開業医会と二重になるのではないかとか、はたして皆様が入会して戴けるか、また、会費が必要になり皆様の出費が増える、入会してどんな「メリット」があるのか、などなど、当初は難問題がたくさんありました。
とにかく、昭和47年に発足準備委員会をつくり、会の大義名分、その目的など方向付けを盛り込んで、定款を作り、そして入会を勧誘したり、その準備に苦労しましたが、皆様の賛成を得て、昭和48年5月発会式となり、定款も承認していただきました。会長に伊藤先生、副会長に大村、有馬、松尾先生、各理事を選出して発足いたしました。
定款に会員の資質向上を図り、会員相互の協調と親睦扶助を推進、本学教室との連携を保つことなどを掲げて、「学術研究会」開催、大学教室との学術交流及び相互援助、医療制度、医療保険、税制等の研究会の開催、などなどとなっておりました。
年代をかさねるにつれ、会長および理事、会員の皆様のご努力により、徐々にその目的を達成していただいております。教室との連携問題、相互援助問題等いろいろあります。まだまだ十分とまではゆきませんし、ご不満もありましょうが、道筋はついた感があります。顧問弁護士をお願いしたり、市整会会報の発行、家族会開催、学術講演会、など多方面にわたり努力していただいております。ありがたいです。
20年経過して、「開業医会」の名称が時代にそぐわないとして、「市整会」に改称され、定款も一部改正されました。
35年を経て会員も200名以上となり、少しは開業医会の「顔」「存在感」が認められる時代となりました。これも各会長、及び各理事の先生方のご努力によるもので、深く感謝致しております。
昭和58年に同窓会内に「奨学基金」を発足させることになり、「お前がそのたちあげ、運営をせよ」との木下会長の命令でした。基金の募集に苦労しましたが、開業医会の先生方が快く、しかも高額の拠出金を出してくださり、その金額は基金の2/3を占めており、今日の奨学基金が存在しているわけです。これは余談ですが、ある先輩が、「お前のツラを見たらいつも金に見えるわ」と笑わせておられたことを覚えております。
この頃より、更に大学医局あるいは同窓会などに対して開業医会の存在価値や「ウエィト」を占めるような時代になったと思います。
今後とも市整会内あるいは会外に対しても更なる発展と盛会をよろしく御願い致します。
